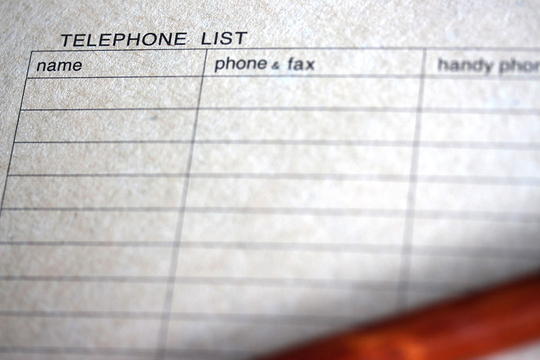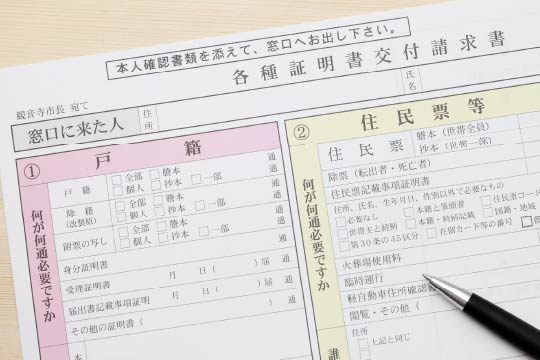もしもの時の備え
葬儀は深い悲しみの中で限られた時間内に多くの手配や準備を行わなければならず、気が付けば葬儀があっという間に終わってしまい、故人をゆっくりと見送る余裕がないということもあります。そうならないためにも、事前に葬儀の準備を整えておくことをお勧めいたします。

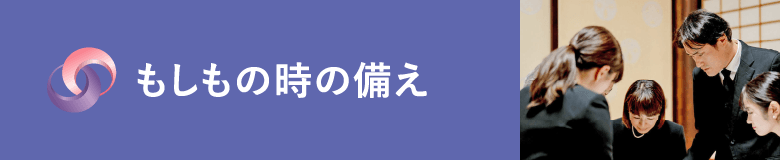
葬儀は深い悲しみの中で限られた時間内に多くの手配や準備を行わなければならず、気が付けば葬儀があっという間に終わってしまい、故人をゆっくりと見送る余裕がないということもあります。そうならないためにも、事前に葬儀の準備を整えておくことをお勧めいたします。